「一生に一度の伊勢参り」その道を辿る。榛原から筋違橋まで。


榛原 1 榛原 2
萩原の辻 本居宣長も泊まったという「あぶらや」左の道標の
初瀬街道との分岐点 前に 今も住んでみえて、年に1.2回内部公開
今回はここからスタート されるらしい大宇陀はこちらに移動しました


榛原 3 榛原 4
「あぶらや」の隣に立派なお屋敷 宗祐寺 周辺に旧家が点在
松の仕立てがすごい! 解体され駐車場になった所も


榛原 5 榛原 6
常夜灯 当日はイベント中でした 墨坂神社「日本書記」にも出てくる、由緒ある神社



船尾 1 船尾 2 檜牧 1
弘法大師の岩清水の 舟尾垣内道標? 御井神社 墨坂神社とは好対照
自販機 1回100円 寛文四年(1664年)建立
高野聖の活躍跡か


自明
不動堂近く 国道脇に旧道の面影が? 酒・煙草・米を販売


高井 1
高井の集落 右手200m位の所にバイパスが 高井の集落祭りの準備が始まっていました
有り、おかげで静かで良い雰囲気 後ろのガードレールがバイパス



高井 2
高井の集落中ほどで左に折れます 頭矢橋のたもとに常夜灯 宮田家と松本家間にある道標
この道標も位置が変わっている


高井 3
宮田家 街道(伊勢側)から見た旅籠・大和家(松本家)


赤埴 1
千本杉 津越家 代々山林業を営んでいて、建物は
昭和41年に改築され、今風の落ち着いた雰囲気
旅籠・大津屋とも言われますが、旅籠は営んで
いないとか 本陣だったとかいわれよく判らない


赤埴 2
「右 いせみち」と刻む。


諸木野 1
庚申塚



諸木野 2
諸木野関所跡



諸木野 3
桜で有名な仏隆寺と伊勢街道の道標。新しそう

諸木野 4
石割峠を控え賑わったという
この宿場町も明治と大正時代の
大火でその風景は失われた。
棚田の田植えも済んで
典型的な日本の山村風景。
町に住んでいると「ほっと」する
光景です。
鉄道が初瀬街道沿いルートを
取った時に杉等の植林に
取組み、今は林業が盛んとか。



石割峠 1
「右 はせみち 左うだみち」 植林された杉の林を抜ける


石割峠 2
峠は切通しで狭く、この小さな「立札」無いと気がつかない



石割峠 3
街道は宝暦5年(1755年)建立の道標の先で右に折れる ここで車道と合流する
「右 いせ 左原山」


上田口 1
山間の風景 旧家の庭に大きな松


上田口 2 黒岩
浄土真宗・専明寺 ここは室生寺への追分 この界隈は旧家が多く残る
でもあり、この界隈に旅籠・茶屋があったという



山粕峠 1
峠は広く茶屋があったという 沢伝いに道がある



山粕峠 1
沢を渡ると「祠」があり国道と合流


山粕 1
集落 かっては人馬で大いに賑わい 専光寺
浄瑠璃も盛んだったとか


山粕 2
春日神社 鞍取峠の入口



鞍取峠 1
入口の道標 この峠は距離は短いが ここにも茶屋があったかも
坂は急で越えるのに30分弱掛かる


鞍取峠 2
坂が緩やかになると林道と合流する 「浄空欣了法師塔」宝永8年(1711年)建立


桃俣 1
白鬚稲荷 ここから町家下の 街道は左手よりカーブする。手前は吉野道
集落が始まる この旅籠街も昭和の大火で失われた



土屋原 1
杉の大木に囲まれた春日神社 境内の「ラッパ銀杏」 白藤稲荷


土屋原 2
川俣辻の道標「左いせ 右はせ」 中央の道路標識の下に道標が建つ


土屋原 3
国道から離れ桜峠に向かう。 峠と言うより「丘」越え。


菅野 1
杉木立を抜けると突然、ドーム型の
小学校が出現!


菅野 2
橋の袂の常夜燈と道標 「太神宮」と刻まれた天保3年
「右 はせみち 左いせみち」 (1833年)の常夜燈


菅野 3
曹洞宗安能寺 室生寺が開かれるまでは 街並み
女人高野と言われたとか 山門左の桜でも知られる



菅野 4
道標「右いせ 左はせ」 街道は右へ


菅野 5
杉木立の中の四社神社 天照大神を始め 氏子さんの玄関の木槌 「四社神社と
四社を祀る古社 秋祭の獅子舞で知られる 上棟祭」書かれている


菅野 6
「伊勢本街道 右旧ちか道 左新(道)」と刻む


神末 1
延喜式・御杖神社 本殿に久那斗神と2神を祀り、境内に神末地区の神社を合祀


神末 2
西町の文政9年(1826年)建立の常夜燈と道標「右 いせみち」


神末 3
橋の袂の旧家 街道は左へ 東禅寺


神末 4
神末地区の東町から西町・牛峠を望む 元旅籠らしい家の玄関 伊勢風注連縄の西限?


神末 5
佐田峠の首切地蔵と自然石の道標 敷津の道標「伊勢本街道
「是与 宮川へ十二里廿一丁」 右旧ちか道 左新(道)」



神末 6
敷津の「太神宮」常夜燈。明治33年建立で新しい


神末 7
岩坂峠の姫石明神縁談や 一気に下る
婦人病に霊験あらたかとか


神末 8
剥き出しの岩石から「岩坂峠」の名が付いたとか 沢と道の区別が無く沢蟹が一杯いる


神末 9
大日如来供養碑 六部経塚


石名原 1
県境を越え国道に合流 すぐ国道と分かれる



石名原 2
「太一」の常夜燈 天保15年(1844年)建立 自然石の道標「いせみち」と刻む


石名原 3
三角柱の道標「すぐいせみち」 「右 なばり 左 はせ」と刻む


石名原 4
払戸の常夜燈「太一常夜燈」と刻む 文政2年(1819年)建立 梅雨に紫陽花が咲いて



石名原 5
中垣内常夜燈「太一」と刻む 文化11年(1814年)建立 自然石の道標「いせみち」と刻む


石名原 6
自然石の道標がある辺り 右下に庚申塚


奥津 1
瀬之原の常夜燈「火袋」が金属に交換してある


奥津 2
柏森呉服店 久しぶりに営業中の店を見ました


奥津 3
かぶとや 趣のある家々が続く



奥津 4
坂本屋 JR駅前の道標「左 はせ新街道」 街並み


奥津 5
尾張屋 元紺屋


奥津 6
まるあ 魚盛
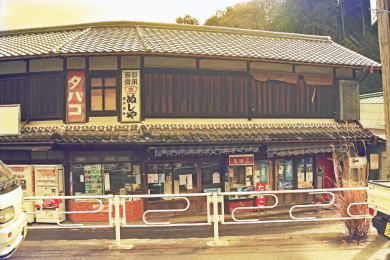

奥津 7
日用百貨「ぬしや」営業していた頃 ’96.02



奥津 8
山内醬油店 以前の警察署 平屋の標準形駐在所に
建替えられました いずれも1996.2撮影
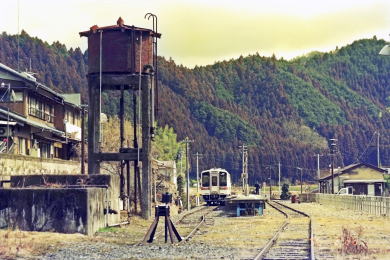

奥津 9
超ローカル線名松線奥津駅、以前の風景 構内と駅舎は新しくなりました



奥津 10
旧旅籠 こちらは変わらない 谷口の常夜燈 曲がり角に建つ




飼坂峠 1
首切地蔵 渓流の沿って急坂を上る 腰切地蔵 沢と道の区別が無くなる
この峠越えは思ったよりハードです。昔、山賊や追剥が出たという


飼坂峠 2
峠 休憩所辺りに茶屋があったとか 東方(伊勢湾側)を見る



飼坂峠 3 多気 1
石段が残る 伊勢湾側は歩き易い 宿場入口 三多気の桜


多気 2
洗い場 旧旅籠?壁が杉皮で仕立ててあります



多気 3
常夜燈 元治2年建立 道標 嘉永6年建立 大橋の旧欄干 今は木造


多気 4
北畠神社 北畠親房、顕家、顕能らを祀る 北畠屋敷跡庭園 12代将軍足利義晴を
左後方から霧山城跡に登れる 迎えるにあたって作庭された
但し「くま注意」の立て札がある。ここは三重県県庁所在地・津市内



多気 5
営業中の旅館「結城屋」 峠の麓の馬頭観音 道標「右 いせ道」



櫃坂峠 1
右に役行者 明和5年の建立 多気不動尊


櫃坂峠 2
峠の旧茶屋?朽ち果てた 東方(伊勢湾側)を見る。集落(中央)は遥か下



櫃坂峠 3
長い急坂が始まる 道が無くなったかと思った 脇を猪が 勢至観音と井戸(下)
駆け抜けた ここは松阪市内



櫃坂峠 4
道標「左 若宮八幡宮道」 山の神 ここまで来ると 道標「右 いせ
本来の位置と異なる? 道はなだらか 宮川へ九り」



長瀬
道標「すぐいせ道」 長瀬不動と弘法大師、燈籠と常夜燈 両泉寺前に建つ庚申塚



横野 1
常夜燈「両宮兼燈」と刻む 庚申祠と常夜燈 街並み 中央が右の庚申祠



横野 2
道標地蔵 柿野神社 境内にある常夜燈。和歌山
街道との追分から移設

柿野 1
和歌山街道との追分 本街道は右へ
猪が出れば「いのしし鍋」屋も出来る


大石 1
「大石宿 これより宮川・・・」と 大石の街並み。山手に
刻まれている 後方が庚申堂 新道が出来残る



大石 2
不動院脇に移設された 不動滝 夫婦滝とも 大石不動院本堂。毎年9月1日に風水害の除災
常夜燈 五穀豊穣を願い「八朔まつり」が行われ賑わう


大石 3
天然記念物「ムカデラン」群落 不動院の前の櫛田川


小片野 1
街道に面して旧三重交通松阪線終点大石駅が 和歌山街道(左)と本街道(生垣に沿う)
有りました 今はバス停とバス駐車場になって との追分 カーブミラー辺りに道標が
います。大石の町からはかなり下流にあります 有ったらしいが発見出来なかった




小片野 2 上茅野 1 下茅野 1
地蔵尊 道標 神社前に移設された 公民館に移設された道標
文政13年建立の常夜燈 「右 さんくう 左まつさか道」
下茅野に常夜燈が2基あったらしいが、移設されたか現地には無い



津留の渡し
船着き場前の 川の中央で底石が直線で無い辺りが 上流に昭和4年、鉄橋が架かりました
石碑 「渡し」のルートか はかり岩はどれ? 「昭和3年 名古屋港 築地鐡工所」製



津留 上牧
道標「左 いせ」 その前に「右 大師道」の道標 左から「道別れ地蔵」「行き倒れ地蔵」
「廻国供養碑」



中牧 鍬形 1
右手に新道が出来、街道はそのまま残る 道別れ地蔵 不動院入口の仏足石



鍬形 2
不動院と不動滝 道標「左 丹生大師道」


井内林
街道は新道と別れ稜線に沿って進む この辺りは、ほ場整理が行われたようで、
左から「廻国供養碑」「いぼ地蔵」
「5代目伊勢三郎物見の松」が纏められている



三疋田 相可 1
歯痛地蔵 弘化2年建立の常夜燈 千鳥ヶ瀬。右から「塞の神」(境の神)
本街道では最大級とか 灯篭(寛政四年)西行法師の記念碑


相可 2
熊野街道との追分 道標の前にある「まつさか餅」長新
左の道標は「伊勢本街道」と 伊勢番外編・伊勢の餅で紹介。
刻まれている 文久三年の建立


相可 3
「鹿水亭」今も料理旅館として営業中 「おんばさん」と呼ばれる母乳神
正面は改装されている
この背後は櫛田川で対岸は射和の町。江戸時代は水銀製品と松阪木綿で大いに栄える。


相可 4 多気 1
町並み 小さな水分社 湧き出る清水が旅人の喉を潤した


西池上 1
金粒丸の看板。西村家にある。 村林家と街道 明治の終わり頃まではこの家が
立派なものでこれ以上風雨 金粒丸を販売していた 江戸に店を出し、
晒すのは惜しい 米・酒・紙を扱い大繁盛だったとか


西池上 2
ここで左の道へ 道標が無いと間違える



朝久田 1
伊勢側から見た「伏し拝み坂」と遥拝碑 内宮摂社・棒原神社 この森の北を通る
中央・切通し上に碑が立っている


田丸 1 田丸城 1
田丸神社と常夜燈 城下に入り 富士見門(長屋門)他に建築物は無い
ここから道が屈折する 街並みはこちら


田丸城 2
南朝・北畠氏ゆかりの城。 天主跡。石組みは打ち込みはぎ?
この石垣は信長の二男・信雄が築いたもの 後に和歌山藩の
領地になり家老久野氏が最後まで城主を務める



田丸 2
熊野街道との交差点から熊野方を見る 今の道標 旧道標 田丸城内にある
御師の過剰接待、古市の夜も良き思い出 玉城中学校内に移転保存
この角を廻れば精進の道が始まる 「紀州街道」と刻まれています
紀州藩主の参勤交代の
道でもありました


玉城 1
狭田国生神社付近。 「オブラート」を発明した小林政太郎の生家。
子供の頃、これで粉薬を包み飲みました(笑)


玉城 2
常夜燈 明治51年6月の建立と刻まれて 宮川 1
いますが、台座はそれ以前の建立と思う 渡し近く



宮川 2
「いせ両宮一里鐙」文政13年建立 案内板の後にある尾崎咢堂(行雄)記念館
川端神社境内に建つ 四季桜が咲いていた


宮川 3
柳の渡しの案内板と柳の渡しがあった辺り 渡れば外宮の
森が見え、参宮街道と合流する筋違橋はすぐ